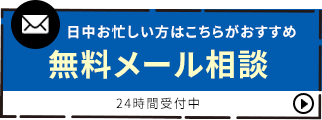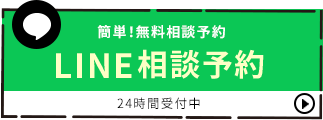一般的に相続の手続きは複雑と考えられています。さらに、認知症の相続人がいらっしゃった場合は特に複雑になりがちです。
以前は、「被相続人(亡くなった方)の方が認知症の場合どうしたらいいのか?」と相談を受けることが多くありましたが、日本全体で平均寿命が伸びるにつれ、相続人が認知症となるケースも多くなってきました。
実際相談に来ていただく方の中には、認知症の兄弟姉妹の意見をぞんざいに扱うこともできず、かといって高度な意思表示は望めない状態でどう相続問題を片づければ良いのか、困り果ててしまう方も多いです。
そこで、どのような点で問題になるのか、どのような準備をあらかじめしておくと相続がスムーズに進むのかを、札幌の中でも高い相談実績を誇る札幌大通遺言相続センターがご紹介します。
認知症の相続人がいると相続にどんな影響がある?バレたくない理由
相続人の中に認知症の方がいる場合、大きく困るのは3点あります。
1点目は「相続放棄するかの否かの決定」2点目は「限定承認の手続き」3点目は「遺産分割協議」を行うタイミングです。
遺産分割協議の話し合いは、遺言・成年後見人の有無次第で相続後に困った事態になりかねません。
なぜ認知症の相続人がいると困るのか?それは相続人全員の意思が必要な手続きが多いためです。
それぞれ具体的にどのように困るのかと、対処法を併せてご紹介します。
相続人が認知症で困るポイント①相続放棄するかの否かの決定ができない
相続時には、亡くなった被相続人の遺産を把握する財産目録を作成します。その際に、プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いのかを確認し、相続するか相続破棄をするかを選択するのが一般的です。
では、認知症の相続人は相続放棄ができるのでしょうか。結論としては、認知症の相続人は相続放棄をすることができません。また、相続放棄の期限は「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」ですが、認知症の相続人がこん睡状態等で被相続人の死亡の事実すらも理解できないといった状況では、相続の開始を知った日が到来しませんので3か月の期限が開始されません。
他の相続人がマイナスの遺産ばかりで相続放棄した場合は、認知症の相続人のみがマイナスの遺産を負担することになってしまう可能性があるため、他の相続人も気軽に相続放棄の選択が取れなくなる点でも困ってしまうポイントです。
相続人が認知症で困るポイント②限定承認の手続き
限定承認とは、相続したプラスの財産を限度額として、相続責務を引き継ぐ手続きのことです。
例えば、被相続人が借金が多く相続したくなくても、形見だけは残したい場合や、今はプラスの遺産が多いが後から借金が出て来そうで不安な場合には限定承認も選択肢に入って来るでしょう。
しかし、限定承認は相続人全員で行う必要があるため、認知症の相続人がいる場合は限定承認ができません。
借金があるものの、どうしても手放したくない不動産がある場合に限定承認を利用しようとしても、認知症の相続人がいるためにその不動産を諦めるといったことも起こりえるでしょう。
相続人が認知症で困るポイント③遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人が複数いる際に、相続する遺産の割合を相続人同士で決めることです。
遺産分割協議はあくまでも相続人全員の合意がなければならないことがポイントです。相続人の1人が行方不明だったり、認知症であったりといった事情があっても同様です。
例えば、認知症の相続人がいる場合、その相続人は話合いを行うこと自体ができないため、そもそも相続人全員での遺産分割協議をすることができず、その後の預貯金解約・不動産名義変更といった相続手続きを進めることもできなくなってしまう恐れがあります。
困ったからって遺産の放置は禁物!!
遺産分割がまとまらず、そのまま放置した場合にはどのような不利益があるのでしょうか。
現金しか遺産がなかったとしても、遺産分割協議が終わらなければ預金の凍結はとかれないため、被相続人の葬儀代金が払えなかったり、認知症の相続人の方の医療費も払えなかったりする場合があります。
不動産を放置した場合は、維持・管理がずさんになるため、老朽化によるトラブルや火災保険が切れたまま火災に合う危険性もあるため、放置するにはリスクがあるでしょう。
また、2024年4月から被相続人名義の不動産名義変更が義務化されました。原則として、被相続人が死亡してから3年以内に不動産の名義変更をしなければならず、これを放置した場合、最悪で10万円以下の過料が科される可能性もあります。
相続人に認知症がいるからと放置していると、損になるばかりか不動産トラブルに巻き込まれて困った自体になる可能性もあるため、遺産は早めの手続きがおすすめです。
認知症の相続人ができる前に行いたい相続対策
現在日本は高齢化社会に突入し、平均寿命も伸び続けています。
実際、相談にいらっしゃる相続人の方は60代以上の方が非常に多いです。被相続人が90代、相続人が60代の状況では、被相続人がいつまでも元気でもその子供が認知症になってしまう可能性もあるでしょう。
そうなれば、相続人の孫の世代を困らせてしまう可能性もあるでしょう。自分の死後、残してしまう相続人を困らせないように、認知症による相続対策も必要です。
皆様が事前にできる3つの対策をご紹介します。
認知症による相続対策①:被相続人に遺言状を書いてもらう
相続人に認知症の方がいらっしゃる場合は、被相続人が遺言書の準備を進めておくと相続がスムーズです。
遺言書は相続人のうち1人でも遺言を認めると有効とされ、一番困ってしまいがちな遺産分割協議が発生しなくなります。
もちろん、相続人が納得しがたい無茶な内容で遺言書を作成した場合、法定相続人が遺留分を請求するなど自体が複雑化する自体が考えられるため、遺言書は相続人たちが納得できる内容が理想です。
他にも、不動産を認知症の相続人に相続させると、管理が難しい場合が多いため遺言で誰に何を相続させるのかはじっくり考える必要があります。
認知症による相続対策②:成年後見制度を利用する
遺言状があれば認知症の相続人がいても遺産分割協議で困ることはほぼ有りませんが、被相続人に遺言を書いてもらうのが心苦しく、頼めない方も多くいらっしゃいます。その場合は、成年後見人をつけるのも一つの手です。
成年後見人制度は家庭裁判所に申し出ることで、利用できます。意思決定に不足がある相続人の権利・財産を保護し、本人の代わりに権利を主張してくれるため認知症の相続人の権利も守ってくれるでしょう。
成年後見人には親族や弁護士・司法書士などが引き受けられるため、安心して任せられます。
もちろん、成年後見人には報酬の支払いが必要になることや、相続が終わっても成年後見人が権利・財産の保護を行うため家庭の都合では好き勝手出来ない部分も出てきますが、認知症になった相続人に取ってはありがたい存在に違いありません。
認知症による相続対策③:家族信託をあらかじめ利用する
被相続人の判断能力がある場合、家族信託がおすすめ。
家族信託とは、財産の所有権を信頼できる親族に移行して管理・運用をしてもらえる制度です。財産は信託財産として扱われるため、使い込みの心配がないメリットもあります。
他にも、相続で面倒に思われがちな名義変更も時間のあるタイミングで行える点や生前贈与ではないため贈与税がかからない点も魅力的です。
相続人がいつ認知症になるかは誰にもわかりませんが、被相続人自身が認知症になる前に対処できる方法はあります。
死後のことを考えるのは気が重いとは思いますが、残された方のためにできることを今の内にやっておきましょう。
まとめ
相続人が認知症だとバレるとどのような困ったことがあるのか、困る点と対処法をご紹介しました。認知症がバレないようにしても、相続に関わるプロは「認知症じゃないかな?」と気づいてしまうことがほとんどです。
どこかでボロが出てしまう前に、相続人が認知症になった際の相続対策をあらかじめ被相続人行うことでスムーズに相続ができるでしょう。
相続のことがわからずお困りの方は、札幌の中でも高い相談実績を誇る、相続のスペシャリスト集団の札幌大通遺言相続センターにお立ち寄りください。
事務所がある大通西4丁目の道銀ビル(札幌市営地下鉄 大通駅直結)までお越し頂き、ご相談を承る方法や、事務所面談・メール・ビデオ通話も選択できます。
メールによるお問い合わせはこちら(24時間365日受付中)
お電話によるお問い合わせはこちら
0120-481-310
当センターは、家族信託(民事信託)をはじめ、遺言作成・成年後見人のサポートや、相続人が行方不明になった場合のご相談を幅広く承っております。
まずは一度、お気軽にお問い合わせください。
プロによる公平中立なアドバイスを受けることで、今後どうすればいいのか道筋を立てることができるようになりますよ。
基本情報
・住所
北海度札幌市中央区大通西4丁目1番地 道銀ビル7階 法務会計プラザ内
地下鉄大通駅 4番出口直結
JR札幌駅 徒歩7分
・電話番号
0120-481-310
・電話対応時間
月曜日~金曜日
9時00分~18時00分