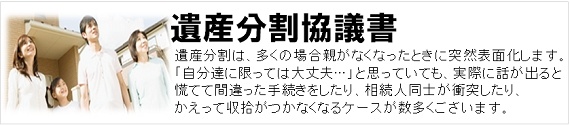遺言書は決して『財産が多いから書く』『財産が少ないから書かない』というものではありません。
そして、自らの死が差し迫ったことによって焦って書くものでもありません。
このことは民法が満15歳から遺言書の作成を認めていることからもわかります。
また、『遺言書はいつでも書けるもの』と考えないで頂きたいのです。
いざ書こうとしたとき、あるいは周囲が「書いて欲しい」と思ったときには、既に字を書くことが難しくなっていたり、【認知症】などによって遺言を遺すための意思能力が欠如していたりという事例が少なくありません。
『必要性を感じない今だからこそ、
しっかりと将来への備えを用意しておく』
【遺言を遺す人】と【遺してもらいたい人】。
ゆっくり話し合える今だからこそ、お互いのために『遺言について考える時間』を作ってみてはいかがでしょうか。
【札幌大通遺言相続センターがお手伝いできること】はコチラ
Case…佐藤大輔さんの場合
佐藤大輔さん(78歳)は妻:博美さん(75歳)、長男:裕太さん(50歳)の3人家族。
今回、大輔さんは将来のことを考え、長男:裕太さんに全ての財産を相続させる内容の公正証書遺言を作成することとしました。
大輔さんの財産は、自宅の土地1筆、建物1棟のほか地方の土地(原野)が4筆。金融資産は預貯金が4か所の銀行、投資信託が1か所の証券会社に預け入れられており、総資産は金5,500万円ほどです。
公正証書遺言 作成の流れ
①戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書など、関係者に関する資料の準備
・遺言者の戸籍謄本、印鑑登録証明書、財産を受け取る相続人・受遺者の戸籍謄本や住民票などが必要となります。
・なお、遺言者が印鑑登録していない場合、新しく印鑑登録せずとも、「認印+顔写真付き身分証明書の提示」で対応することが可能です。
・NPO法人への寄付を遺言書の内容としたい場合には、法人の登記事項証明書なども必要です。
②不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、通帳の写しなど、財産に関する資料の準備
・財産の内容、金額を特定するための関係資料が必要です。
・不動産の場合には「登記事項証明書」や、毎年役所から送付される「固定資産税・都市計画税 納税通知書」が必要となりますが、固定資産税が発生していない不動産については「固定資産評価証明書」を市区町村役場・市税事務所に請求する必要があります。
・預貯金については通帳の写し、株式や投資信託といった有価証券については証券会社から送付される「取引残高報告書」の写しが必要書類となります。
③遺言内容の決定
・誰に、どの財産を、どの程度相続させるのか、を中心に遺言内容を決定していきます。
・特に「遺留分の侵害」や「予定している相続人が遺言者より先に死亡した場合、財産の承継先をどうするのか」といった点に注意する必要があります。
・「遺言執行者」を誰にするのか、という点も非常に重要です。遺言者が年をとり、亡くなる際には、当然ながら遺言執行者も同様に年をとり、場合によっても健康上の問題を抱えているかもしれません。個人を指定する場合には死亡のリスクもあり、当センターでは司法書士事務所を会社組織化し、司法書士法人として遺言執行者をお引き受けすることで、これらの問題を解消しています。
④遺言文案の作成
・決定した遺言内容をもとに、公正証書遺言とするための文案を作成します。
・基本的に公証役場とのやりとりによって作成しますが、検討した文案が記載された遺言書によって、相続開始後に実際にお手続きをすることができるのか否か、関係機関に事前問い合わせを行わなければならないケースもあります。
⑤遺言公正証書の作成
・前記④の段階で提出が未了であった必要書類を公証役場に提出します。
・遺言作成のための日時を事前に調整し、公正証書遺言の作成期日を迎えます。公証役場を訪問することも、公証人に自宅や病院、入居施設に出張してもらうことも可能です。ただし、公証役場は役所であるため、通常は平日の9:00~17:00の間で時間設定することになります。
・当日同席可能な証人2名以上の設定も必要です。
・当日は公証人が遺言内容を読み上げて確認し、遺言者・証人が署名捺印し、公正証書遺言は完成となります。
必要書類
■ 遺言者:大輔さんの現在の戸籍全部事項証明書(1通)
■ 遺言者:大輔さんの印鑑登録証明書(1通/遺言書作成時点において発行後3か月以内の新しいもの)
■ 財産を受け取る長男:裕太さんの現在の戸籍(全部事項証明書または個人事項証明書のいずれでも可/1通)
・財産を受け取る方が遺言者の推定相続人(=将来、相続人となる方)であることを確認するために必要です。
・同じ推定相続人であっても、遺言者の兄弟姉妹や甥姪に財産を承継させたい場合、準備が必要な戸籍の範囲の範囲が異なりますので、注意が必要です。
・財産の承継先が推定相続人ではない場合、戸籍に代えて、住民票が必要です。
■ 所有不動産に関する登記事項証明書
・遺言書に不動産の所在等を明示する場合に必要です。
・事前登録によりインターネットで取得することができる登記情報でも代替可能です。
■ 所有不動産に関する最新年度の固定資産税・都市計画税 納税通知書
・公証人手数料算出のためには遺言書に記載する財産金額を確認する必要があり、不動産の評価額確認資料として、固定資産税・都市計画税 納税通知書が必要です。
・固定資産税が発生していない不動産については、この納税通知書が発行されないため、「固定資産評価証明書」や「名寄帳」を別途取得する必要があります。
■ 通帳、取引残高報告書の写し
・預貯金、株式、投資信託等の金融資産の内容確認及び金額確認のために必要です。
『相続』が発生すると、亡くなられた方の財産分配は相続人の遺産分割協議によって決められることとなります。
しかし、当事務所に頂くご相談には、『遺産の分け方はまだ決まっていない』という内容のものが少なくありません。
肝心の財産の持ち主が亡くなられているがために、それぞれの相続人の主張が衝突してしまうことに原因があります。
『自分は死んだ母の入院時の世話をしたから多くもらえるはず』
『あなたは亡くなった父の預金を自由に使っていたのだから その分はもらえないでしょう』
『保険金が貰えるんだから、その分相続分は少なくなるはずだ』
『土地と建物はくれると、遺言書は無いけどそう言っていた』
──── 思い当たるところはありませんか?
実はこのようなお話の多くが、資産をお持ちの一部のご家庭ではなく、極々普通のご家庭で起こっている話なのです。
本当に相続人の話し合いだけに任せてよいのでしょうか?
遺産分割協議が整わないばかりに【遺産分割調停】へと発展し、何年もの間争い続けているケースもまま見受けられます。
自らが築き上げた財産に対して最期まで責任を持ち、遺された遺族が1日でも早く元の生活に戻れるように備えておく…
ご相談頂く相続トラブルの多くが、『遺言書』という故人の明確な意思さえ遺されていれば、防ぐことができたものばかりなのです。
【札幌大通遺言相続センターがお手伝いできること】はコチラ
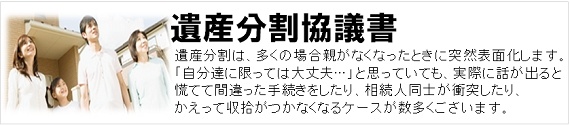
遺産分割協議について、手続きの進め方、書類の書き方、注意事項、審判についてそれぞれまとめております。詳細は以下をご参照下さい。
遺産分割には『指定分割』『協議分割』の2つがあり、
遺産分割の方法としては『現物分割』『換価分割』『代償分割』及び『共有分割』と4つの方法があります。
詳しくは、遺産分割協議の進め方のページをご覧ください。
『遺産分割協議書』は法律上作成が義務付けられているものではありません。
しかしながら、後々のトラブルを回避するためにも作成をお勧めしています。
では具体的には何を記載すればよいのでしょうか?
詳しくは、遺産分割協議書の書き方のページをご覧ください。
遺産分割協議はただの話し合いではない、法律上の行為です。
何度も行なうことがないように、ルールを守ってしっかり話し合いましょう。
詳しくは、遺産分割協議の注意点のページをご覧ください。
遺産分割協議がうまくいかない場合には、裁判所の力を借りることになります。
裁判所での話し合いである『調停』と、裁判所の決定である『審判』とあります。
詳しくは、遺産分割調停と審判のページをご覧ください。

札幌大通遺言相続センターでは、初回無料の相続相談会を実施しております。
まずはお電話にて、ご相談の概要をお聞かせください!

まずはお気軽にお問合せ下さい!
担当の行政書士 ・ 司法書士のスケジュールを確認のうえ、ご相談の日程とお時間を調整させていただきます!
【営業時間】9:00-18:00
※ ご相談は相続人の方、遺言書を検討されている方及びそのご親族様に限定させていただいております。

無料相談では、相続専門の資格者が、しっかりとあなたのお話をお聞きいたします。
時間を気になさらずに、安心してお話ください!

また、相続手続に関する書類作成から裁判所に提出する書類、法務局に提出する申請書類の作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明をさせていただきますので、どうぞご安心ください!
納税(資金)対策
相続税は金銭で一括納付をすることが原則になっています。
不動産やその他の動産で納付することは条件付きとなりますし、売却して金銭に換価することも本望ではないことが多いでしょう。
そういったときに、よく対策として使われるのが「終身保険」です。
保障が一生続くため、死亡時に必ず保険金が受け取れ、現金が手元に残るのです。
とは言え、相続税額は一般的に高額です。
それだけで支払えるような保障額の保険に加入しようとすると、保険料も高額になってしまいます。
その対策として、保険期間を長くした「定期保険」や「定期付終身保険」が利用されることが多いようです。
生命保険を活用するメリット
1)受け取る死亡保険金には非課税枠があります
契約者、被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、受け取った保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
そのうち法定相続人数×500万円が非課税になります。
例えば、夫が死亡して妻が2,000万円の保険金を受け取った場合、子供が2人いたとすると、法定相続人3人×500万円=1,500万円が非課税となり、残りの500万円が他の相続財産と合算され、課税対象となります。
2)加入と同時に納税対策ができます
保険に加入したのと同時に資金が準備できることになります。
銀行預金などの積立とは大きく異なる部分です。
3)保険金受取時まで課税は発生しません
生命保険の配当金は、受け取った保険金と一緒に相続財産として扱われ、契約途中で課税されることがありません。
一方で、銀行預金で利息に20%の源泉徴収がされてしまいます。
4)現金で受け取れます
相続税は、原則として発生から10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。
もし不動産などの固定資産だけを相続したような場合、売却して資金を調達することも少なくないようです。
保険金はもちろん現金として受け取れるので、固定資産の売却をせずに済むかもしれません。
もちろん、相続税の納付には、延納や物納という方法もありますが、利子もかかる上、手続が面倒です。
なお、固定資産に全く手をつけずに相続税納付を行いたいのであれば、受け取る死亡保険金にかかる相続税分も計算に入れて、保障額(保険金額)を決める必要があります。
現物分割に生命保険を利用する
遺産の大半が不動産だという場合、相続人が数人居れば、家を分割するわけにもいきません。
現実的にはよく発生するケースで、このときに生命保険を上手に使うことが出来ます。
この場合不動産は遺言で一人に遺贈し、他の人を生命保険の受取人に指定して、その死亡保険金を分配することで帳尻を合わせられるのです。
ただし、保険金額は遺留分の額以上にしておくことが大事です。
代償分割に生命保険を利用する
商売をしている場合、遺産分割すると商売ができなくなってしまうということがあります。
このような場合、「代償分割」という方法が使われます。
「代償分割」とは、相続人の一人が財産を受ける代わりに、他の相続人には相当の金銭や別の資産をその代償として支払うというものです。
この場合、代償分割の支払いのための資金を生命保険で準備することが出来ます。
財産を受ける人を死亡保険金受取人に指定しておけば、一度受け取った保険金を他の人に支払うことができます。
同族会社などの場合、株式の多くを社長が持っているケースが多いようです。
また、会社を子供に継がせたいと希望している経営者も多いようです。
こういった場合、社長が死亡して保有していた株式を会社の経営に関係のない、後継者以外の相続人に分割すると、その後それらの相続人から会社に対して自社株の買い取り請求を受け、経営を圧迫するといった事態にもなりかねません。
会社経営を安定的に承継するためには、後継者一人に自社株を相続させることが必要です。
そこで、生命保険を活用した遺産分割対策が有効になるのです。
相続税の納税資金の考慮
相続対策でこれまでよく採用された方法に、無理な借金により、貸しマンションやアパートの建築をして財産評価額を下げるという方法があります。
この方法には一定のリスクが伴い、納付する相続税額を節税する対策は危険だと言う専門家も少なくありません。
そういう意味では、財産評価額を下げる対策ではなく、納税資金に換価できる資産、不動産を用意することによる、納税資金準備対策が重要でしょう。
換金性を高めた資産などを生前から準備しておき、相続発生後に直ちに換金することで相続税を納付しようとするものです。
特に換金しにくい不動産等を換金化しやすいような資産構成に代えておくことが代表的です。
例えば、すぐに売却できるような更地で持っておくこと、その間有効な活用をすることが挙げられます。
注意点は、相続税課税時点において、納税義務者(特に奥様などの配偶者)に、換金性の高い資金が分配されるような配慮を、遺言書で記載しておくことです。
資産を残す側が、困りがちなケースを想定して、最低限やっておかなければならないことと言えるでしょう。
というのも、換金性の高い資産でも、保有している土地取引に時間がかかってしまうことが多く、譲渡所得税等の発生もあるからです。 物納する場合も物件自体が物納要件を満たしていることが求められ、更に認可手続に時間がかかります。
しかも、物納認可が下りないといったケースもあり、これは大きなリスクです。
そこで、相続税の納税のための資金準備をしておく必要性が発生するのです。
納税資金が足りない場合の対策
納税資金対策として、よくご提案させていただいている方法をご紹介します。
短期的なものとしては、
1)銀行から借入する
2)死亡退職金・弔慰金を活用
3)相続資産の売却
4)納税資金の生前贈与
5)延納・物納を利用する
があります。
ただし、短期的というのは、狙ってそうするのではなく、結果的にその必要性があったということが大半です。
出来る限り計画的に、長期的な視野で取り組まれることをお薦めします。
長期的な対策として、計画的に取り組めることの代表例を挙げると、
1)生命保険に加入する 2)土地活用により賃貸収入を得る
3)賃貸用不動産を譲渡する
どれも専門家にアドバイスを求めた方が無難な対策です。
信頼できるアドバイザーを探しましょう。
納税資金の過不足分析
必要となる納税資金に対して、相続財産と相続人所有の金融資産(現預金・生命保険金・上場有価証券等)がいくら準備できるかを試算し、相続税を支払う能力があるかチェックすることが出来ます。
不足していれば、対策が必要でしょう。
一般に、相続税の支払能力の判定は、
納税資金÷相続税×100
で求めます。
この比率が100%よりも小さければ小さいほど対策が必要です。
納税資金の不足を解消するためには、
(1)節税対策により相続税額を軽減すること
(2)納税資金対策により資金を増やすこと
の両面からのアプローチが必要です。
納税資金対策では「生命保険」の上手な活用が最も有用です。
終身保険の有期払いで加入すれば、確実に死亡保険金を相続税の納税資金に充当できます。
支払保険料は相続税の分割前払いと考えることもできます。
これにより、所有土地等を譲渡または物納することなく、相続税の納税を完結させることもできます。
経営承継円滑化法
平成20年2月に「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律案」が国会に提出されました。
これを受け、平成21年度税制改正で「取引相場のない株式などに係わる相続税の納税猶予制度」を中心とする事業承継税制が創設されます。
税制改正の背景
1)これまでは生前贈与で後継者に移転した自社株式についても、遺留分の基礎財産に加えられるため、遺留分侵害分を取り戻されることがよくありました。
要するに、自社株式などを後継者へ移転した分は、遺留分権利者から遺留分の減殺請求をされた場合に、遺留分の算定の基礎財産に加えられ、遺留分侵害分が非後継者に移転する危険性があったのです。
2)相続税の算定にも問題がありました。
現行の税法では、相続税の算定時に合算される額は贈与時の評価額ですが、民法上の遺留分の算定では「相続開始のときにおける価額」となっています。
そのため、生前贈与後に後継者の貢献により株式価値が上昇すると、上昇した分だけ相続時点の遺留分減殺請求の額が増え、後継者の事業承継意欲を阻害していました。
新税法で何が変わるのか
今回の「経営承継円滑化法」は、事業承継の阻害要因だった民法の遺留分制度に対しての特例です。
また、「株式等に係る納税猶予制度」は、事業承継の阻害要因だった相続税負担に対しての納税猶予措置なのです。
上記の2つの課題に対して以下の導入効果があると考えられます。
1)この制度を活用することによって、一定の要件を満たす後継者へ先代経営者から贈与された自社株式、その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外できるようになります。
その結果、事業承継に不可欠な自社株式などの生前贈与が確実になるのです。
2)改正により、遺留分の算定時に、生前贈与株式の額を当該合意時の評価額であらかじめ固定できるようになります。
その結果、生前贈与後の後継者の貢献による株式価値上昇分は遺留分減殺請求の対象外となり、後継者の経営意欲も阻害されなくなるのです。
死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者が受任者に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。
遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、これは法定の遺言事項にあたりません。
遺言者の希望ということで、遺産の分配等に関する条項に続く付帯事項としてなされることになります。
葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。
一方で、この死後事務委任契約は原則として委任者の死亡によって終了しますが、委任契約の当事者である委任者と受任者は、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることができますので、委任者は受任者に対して短期的な死後の事務を委任することができます。
晩年の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。
確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定しておく、遺言執行者を指定して、その遺言執行者との死後事務委任契約を締結する方法も考えられます。
契約内容の注意点
費用の負担について明確にしておく必要があります。
任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。
遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。
ご本人がご希望される内容にて、その費用分を明確にし、その預託金として預けたとしても、相続財産に混在してしまう危険性や、預託が長期にわたる場合には、不正が発生することを事前にご理解して頂く必要があります。
また、80歳まで契約可能な保険を活用される方も増えており、生前予約された分の保障を保険とお考えのようです。
亡くなった後の事務手続き
・委任者の生前に発生した債務の弁済
・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
・親族関係者への連絡
・家財道具や生活用品の処分に関する事務
それぞれを必要に応じて行うことも可能です。
「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお薦め致します。
財産管理委任契約とは、自分の財産管理や生活する上での事務について、代理権を与え、委任する契約です。
任意代理契約とも呼ばれます。
財産管理委任契約の特徴は、
■ 当事者間の合意のみで効力が生じる
■ 内容を自由に定めることが出来る
ということでしょう。
財産管理委任契約と成年後見制度の違い
判断能力の減退があった場合に利用できるのが成年後見であり、財産管理委任契約は特にその制限がない点が大きな違いです。
また、裁判所が間に入ることなく、当事者間で自由に設計出来る点も異なる部分でしょう
すぐに管理を始めなければならない場合、判断能力が徐々に低下するその前から管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合などに有効な手段といえます。
財産管理委任契約のメリット
・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる
・開始時期や内容を自由に決められる
・本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能
>財産管理委任契約のデメリット
・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない
・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。
法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選任します。
しかし、後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補を記載しておけば考慮してもらえます。
ただし、家庭裁判所の家事調査官が調査して、相続関係等から不相当であるとの判断がされると、候補が記載されていても別途選任されます。
候補が記載されていないときは、家庭裁判所が司法書士などから適任者を探して、選任されます。
また、後見開始の審判申立書に書く候補者を誰にするべきかについては、人によって考えが異なります。
過去の例では、子供や兄弟、配偶者等の親族がなることが多いようです。
理想的なのは、
■ お金に関して絶対の信頼をおける方
■ 面倒見の良い方
■ 近所で生活している方
■ 本人より若い方
でしょう。
最近は、身上監護は親族、財産管理は司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えてきつつあります。
財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いのでしょう。
また、相続人が複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を行うのがよい場合もあります。
任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。
ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。
1) 未成年者
2) 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
3) 破産者
4) 行方の知れない者
5) 本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族
6) 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方がきめの細かい後見ができるかも知れませんが、財産管理が中心であれば司法書士の方が適切な管理ができるかもしれません。
注意をしなければならないのは、後見人にも将来何があるか分からないことです。
平均寿命が長くなっている現状を考えると、最も安心なのは、信頼できる法人を後見人にする「法人後見」だと思われます。
現在法人後見を実施しているのは、全国的には、司法書士会が設立した(社)成年後見センター・リーガルサポートがあります。
任意後見契約
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。
任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。
上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。
任意後見のメリット
・成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができること
・契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
・家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること
などの良いところがあります。
任意後見のデメリット
・死後の処理を委任することが出来ない
・法定後見制度のような取消権がない
・財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける
・本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、実際に管理は出来ない
良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることをお勧めします。