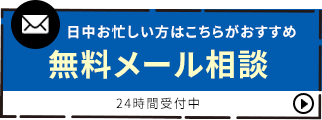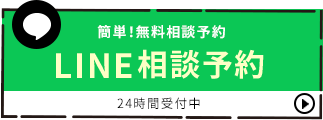「所有している不動産を、将来子どもに確実に相続させたい」
「認知症になった時のために、不動産の管理を家族に託しておきたい」
「賃貸物件の管理をもっとスムーズに行いたい」
このように、不動産の管理や承継についてお考えの方にとって、「家族信託」は有効な選択肢の一つとなり得ます。しかし、
「家族信託って、全ての財産を対象にするものなの?」
「不動産だけを信託することもできるの?」
「もしできるなら、どんなメリットやデメリットがあるんだろう?」
といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、不動産のみを対象とした家族信託について、その基本的な仕組みから、具体的なメリット・デメリット、手続きの流れ、そして費用相場までを詳しく解説します。
この記事を読むことで、不動産に特化した家族信託がご自身のニーズに合っているかどうかを判断し、具体的な行動に移すための第一歩を踏み出せるでしょう。
家族信託で不動産のみの信託は可能
結論から申し上げますと、家族信託は不動産のみを対象として行うことが可能です。 家族信託は、特定の財産を特定の目的のために、信頼できる家族に託す仕組みです。そのため、預貯金、株式、有価証券など、様々な種類の財産を信託の対象とすることができますが、もちろん不動産「のみ」を信託することも何ら問題ありません。
家族信託の基本的な仕組み
改めて、家族信託の基本的な仕組みを確認しておきましょう。家族信託では、主に以下の三者が登場します。
| 委託者 | 財産を託す人(親など) |
| 受託者 | 財産を託され、管理・運用・処分を行う人(子など) |
| 受益者 | 信託財産から利益を受け取る人(多くの場合、委託者自身やその家族) |
委託者は、受託者との間で「信託契約」を結び、自身の持つ特定の財産(この場合は不動産)を受託者に託します。
受託者は、信託契約の内容に従い、受益者のためにその不動産を管理・運用する義務を負います。
不動産のみを家族信託することも可能
上記のように、家族信託は個別の財産ごとに設定することができますので、不動産のみを選んで信託契約を結ぶことが可能です。
例えば、「自宅の管理と将来の相続対策のために自宅のみを信託する」「収益物件の管理を円滑にするために賃貸マンションのみを信託する」といった活用方法が考えられます。
家族信託で不動産を管理するメリット
不動産のみを家族信託することには、特有のメリットとデメリットが存在します。これらをしっかりと理解しておくことが、適切な判断をする上で非常に重要です。
①認知症対策としての活用できる
不動産を所有している方が認知症を発症した場合、その不動産の売却、賃貸、担保設定などの処分行為や管理行為が困難になる可能性があります。成年後見制度を利用することもできますが、手続きが煩雑であったり、柔軟な財産活用が難しかったりする場合があります。
家族信託を活用すれば、委託者の判断能力が低下する前に、信頼できる家族(受託者)に不動産の管理・処分権限を移しておくことができます。これにより、認知症発症後も、受託者が委託者の意向や受益者の利益に基づいて、柔軟かつ継続的に不動産の管理・活用を行うことが可能になります。
②遺言や成年後見制度とのハイブリッドとして使える
不動産の承継対策としては遺言が一般的ですが、遺言はあくまで亡くなった後の財産の移転について定めるものです。認知症対策としての機能はありません。
一方、成年後見制度は、判断能力が低下した方の財産管理や身上監護を支援する制度ですが、家庭裁判所の監督下に置かれるため、自由な財産活用には制約があります。
家族信託は、生前の財産管理と死後の財産承継の両方を、比較的柔軟に設計できる点が大きな特徴です。特に不動産においては、遺言では実現できないような、例えば「一次相続は配偶者、二次相続は長男」といった、より細やかな承継方法を設定することも可能です。
家族信託で不動産を管理するデメリット
不動産のみを家族信託するデメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。
①登録費用(信託登記費用)
不動産を信託する場合、所有権移転登記に加えて、信託登記を行う必要があります。これにより、通常の不動産登記費用に加えて、司法書士への報酬や登録免許税などの費用が発生します。
②信託契約の管理
信託契約の内容に従い、受託者は受益者のために適切に不動産を管理・運用する義務を負います。これには、賃貸管理、修繕、固定資産税の支払いなどが含まれ、受託者の負担が増える可能性があります。
③信託期間中の柔軟な対応の制約
信託契約の内容によっては、信託期間中に不動産を売却したり、新たな活用方法に変更したりする際に、受益者や他の関係者の同意が必要になるなど、一定の制約が生じる場合があります。
④専門家への相談費用
信託契約書の作成や登記手続きなど、専門家のサポートが必要となる場面が多く、その都度費用が発生します。
不動産のみを家族信託する際の具体的な流れ
不動産のみを家族信託する場合、基本的な流れは以下のようになります。
STEP1.家族信託契約書の作成
家族間で十分に話し合い、信託の目的、信託する不動産、受託者、受益者、信託期間、管理・運用方法、信託終了時の財産の帰属などを具体的に決定します。
これらの内容に基づき、信託契約書を作成します。契約書の内容は、将来のトラブルを防ぐために、専門家(弁護士や司法書士)に相談しながら慎重に作成することをおすすめします。
STEP2.不動産の信託登記手続き
作成した信託契約書に基づき、信託する不動産の登記手続きを行います。具体的には、所有権移転登記(委託者から受託者へ)と信託登記を法務局に行います。
この手続きは専門的な知識が必要となるため、司法書士に依頼するのが一般的です。
信託銀行・司法書士への相談ポイント
不動産のみの家族信託を検討する際、信託銀行や司法書士などの専門家に相談することは非常に有効です。
| 信託銀行 | 信託に関する幅広い知識や経験があり、信託契約の組成から財産管理・運用までをサポートしてくれる場合があります。ただし、手数料が高めに設定されていることが多いです。 |
| 司法書士 | 不動産の登記手続きの専門家であり、信託登記に関する知識や経験が豊富です。信託契約書の作成や相談にも対応してくれる事務所もあります。 |
相談する際には、以下の点を明確に伝えるようにしましょう。
- 不動産のみを信託したいと考えていること
- 家族信託の具体的な目的(認知症対策、相続対策、収益物件の管理など)
- 家族構成や財産の状況
- 予算や希望するサポート範囲
家族信託の手続きにかかる費用相場
不動産のみを家族信託する場合にかかる費用の相場は、以下の通りです。
| 司法書士・弁護士・税理士の費用比較 | |
| 司法書士 | 信託契約書作成のサポート(10万円~30万円程度)、信託登記費用(8万円~15万円程度、不動産の評価額や数による) |
| 弁護士 | 信託契約書作成・リーガルチェック(20万円~50万円程度、契約内容の複雑さによる)、紛争予防のアドバイス |
| 税理士 | 税務相談・税金対策(5万円~、信託財産の規模や相談内容による) |
初期費用としては、不動産を含む場合、50万円~100万円程度を想定しておくと良いでしょう。不動産を含まない場合は、30万円~50万円程度が目安となります。維持費は、信託財産の種類や管理状況によって異なります。
※上記はあくまで目安であり、事務所や契約内容によって大きく変動します。
まとめ
家族信託は、不動産のみを対象としても有効な財産管理・承継の手段となり得ます。認知症対策やスムーズな相続、収益物件の効率的な管理など、様々なメリットが期待できる一方で、登録費用や信託契約の管理といったデメリットも存在します。
不動産のみの家族信託を検討する際には、本記事で解説したメリット・デメリット、手続きの流れ、費用相場をしっかりと理解し、ご自身の状況や目的に合わせて慎重に判断することが重要です。
手続きを進めるにあたっては、家族間で十分に話し合い、信頼できる専門家(司法書士、弁護士、税理士など)に相談しながら、最適な信託契約を設計することをおすすめします。専門家のサポートを得ることで、複雑な手続きをスムーズに進め、将来の安心へと繋げることができるでしょう。