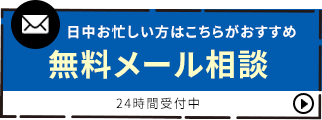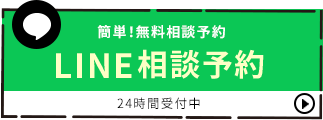「夫に前妻の子がいるが、夫が亡くなったとき、前妻の子に夫の財産を相続されてしまうのだろうか?」
「夫が亡くなったときに、前妻の子がいることで何かトラブルは起きないのだろうか?」
お客様のご相談を承る中で、こうしたご質問をいただくことがよくあります。
今回は、札幌大通遺言相続センターがこれらの疑問にお答えいたします。
そもそも相続とは
「相続」とは、故人の財産や権利義務を相続人が承継することをいいます。
相続人の範囲と順位は民法で定められています。故人の配偶者は常に相続人となり、配偶者に加えて相続人となるのは、以下の範囲です。
① 故人の子(子が故人より先にお亡くなりの場合は孫)
② ①がいない場合、故人の直系尊属(父母や祖父母)
③ ①②がいない場合は故人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人より先にお亡くなりの場合は甥姪)
故人の預貯金の解約や不動産の名義変更などのいわゆる相続手続きにおいては、原則、相続人全員の合意が前提となります。
相続人全員が故人の財産の分割方法を協議した上で、合意している必要があり、この協議のことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご覧いただければと思います。
【争続を防ぐ】遺産分割協議書とは?協議の流れや書き方・注意点を解説
前妻の子は相続人となるのか
では仮に夫が亡くなった場合、前妻の子は相続人となるのでしょうか?
結論から申し上げますと、夫が亡くなった場合、前妻の子も相続人となります。
前妻の子も夫の子であることに変わりはなく、故人の子(前述の①に該当)として相続人となります。
したがって、夫が亡くなったときは、前妻の子も交えて相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、遺産分割協議の結果次第では前妻の子が夫の財産を相続する可能性があります。
夫の財産を前妻の子に相続させない方法
夫が亡くなったとき、前妻の子も相続人になることは前述の通りですが、夫の財産を前妻の子に相続させないためにはどのような方法があるのでしょうか?
遺産分割協議による事実上の相続放棄
遺産分割協議を行い、前妻の子が故人の財産を相続しないことに、相続人全員が合意するという方法です。このような遺産分割協議をすることを、家庭裁判所に申請して行う相続放棄と区別して、「遺産分割協議による事実上の相続放棄」と呼ぶことがあります。
家庭裁判所に申請して行う相続放棄の場合、相続放棄が受理されると、申請者は初めから相続人ではなかったという扱いになり、積極財産(預貯金や不動産など経済的な価値がある財産)及び消極財産(債務などのいわゆる借金)の一切を放棄することとなります。
一方、「遺産分割協議による事実上の相続放棄」の場合、相続人としての地位はそのままに積極財産を相続しないとすることができます。なお、消極財産は遺産分割協議の対象とはならず、消極財産を相続しないとすることはできません。消極財産についても相続人が遺産分割協議において分割方法を決めることができてしまうと、債権者に不利益が及ぶ可能性があるためです。
夫が遺言書を残す
故人が遺言書を残していた場合は、遺産分割協議を行う必要がなく、遺言書の内容に沿って故人の財産を分割することが可能です。
夫が前妻の子以外に自分の財産を相続させる内容(全財産を妻に相続させる等)の遺言書を残すことで、前妻の子に夫の財産を相続させないようにすることが可能です。
ただし、夫が亡くなったとき、夫が残した遺言書の内容が前妻の子の遺留分(法律で最低限保証された分割割合)を侵害していた場合、前妻の子から遺留分を請求される可能性があります。遺留分を請求された場合、遺留分に相当する金額を請求者に支払うこととなります。
遺留分については以下の記事でも解説しておりますので、ご覧いただければと思います。
遺言書の書き方例!全財産を妻や子供など特定の人に相続させる方法を解説します
なお、遺言書を作成する場合、確実性の高さから、公正証書遺言の作成をお勧めしております。
公正証書遺言については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご覧いただければと思います。
前妻の子がいる夫の相続におけるトラブル例
前妻の子の住所や連絡先がわからず遺産分割協議が進まない
夫が遺言書を残さずに亡くなってしまった場合、前妻の子を含め相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、「前妻の子の住所や連絡先がわからず遺産分割協議が進まない」というご相談を承ることが度々あります。
遺産分割協議がまとまらない限り、故人名義の預貯金の解約や不動産の名義変更はできませんので、相続手続きが滞ってしまいます。
このような場合の対策としては、前妻の子の住民票または戸籍の附票を区役所で取得し、前妻の子の住所を確認するという方法が考えられます。前妻の子の現住所を確認し、手紙等で連絡を試みるということです。
通常、住民票を取得することができるのは本人または同一世帯の方に限られ、戸籍の附票を取得することができるのは本人、配偶者、同一戸籍の方、直系血族(父母・祖父母・子・孫)に限られます。しかし、相続が発生している場合、相続人同士であれば他の相続人の住民票や戸籍の附票を請求することが可能です。
前妻の子と揉めてしまい遺産分割協議がまとまらない
現妻(もしくは現妻との子)と前妻の子では関係が希薄な場合も多く、遺産分割協議の中で感情的な対立が起こってしまい、遺産分割協議が一向にまとまらないというトラブルです。
このような場合に取りうる方法としては、弁護士を代理人として立てて遺産分割協議を進める方法や、家庭裁判所へ遺産分割調停(裁判所の力を借りながら遺産分割の合意を目指す手続き)の申立てをするという方法が考えられます。当事者だけで遺産分割協議を行うことが難しい場合は、第三者の力を借りるということです。
ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回は、夫の財産を前妻の子に相続させない方法や、前妻の子がいる夫の相続におけるトラブル例についてご紹介しました。
最後に、この記事のポイントを振り返りましょう。
前妻の子がいる夫の相続においては、前妻の子も相続人となり、相続手続きをするには前妻の子を含め相続人全員の合意が必要
前妻の子に相続させない方法
- 遺産分割協議による事実上の相続放棄
- 夫が遺言書を残す
前妻の子がいる夫の相続におけるトラブル例
- 前妻の子の住所や連絡先がわからず遺産分割協議が進まない→前妻の子の住民票や戸籍の附票を取得し、住所を確認する
- 前妻の子と揉めてしまい遺産分割協議がまとまらない→弁護士を立てるなり、遺産分割調停の申立てを行う