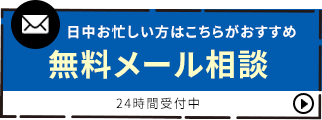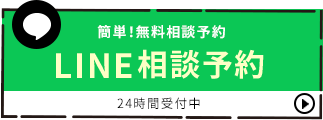「親名義の預金口座を子供名義に変更したいが、どのような方法があるのか?」
「それに伴って税金上の問題はないのか?」
お客様のご相談を承る中で、こうしたご質問をいただくことがよくあります。
今回は、札幌大通遺言相続センターがこれらの疑問にお答えいたします。
親から子への銀行預金口座の名義変更
結論から申しますと、親名義の預金口座を子の名義に変更することは、ほぼできません。
本記事の執筆にあたり、複数の金融機関に確認を取りましたが、
「親の生前・死後にかかわらず、親名義の預金口座は名義変更できず、預金を払い出した上で子の名義の預金口座に移動させるのが一般的である」
との回答が大多数でした。
なお、一部金融機関では、「親の死後に限り、定期預金口座は名義変更が可能である」との回答もありましたが、普通預金では名義変更はできないとの回答でした。
全ての金融機関へ確認を行ったわけではありませんので断言はできかねますが、親名義の預
金口座を子の名義に変更することは難しいと考えるのが無難でしょう。
親から子へお金を移したい場合
前述の通り、親から子へお金を移したい場合には、親名義の預金を払い出した上で子の名義の預金口座に移動させることとなります。
親から子へお金を渡す行為は、親の生前に行う場合は「贈与」、死後に行う場合は「相続」となります。
「贈与」と「相続」では、手続き手順や関係する税金が異なります。
預貯金の贈与
「贈与」とは、当事者双方の意思で、当事者の一方が、財産を無償で相手方に与える法律行為のことをいいます。
生前に親から子へ預貯金を無償で渡す行為は「贈与」となります。
預貯金を贈与する手順
- 贈与契約書を作成
- 預貯金を移動
- 贈与税の申告(必要な場合のみ)
1.贈与契約書を作成
贈与は契約書を作成せずとも、当事者双方の口頭の意思表示のみで成立します。しかし、契約書を作成していなかったことで、後に当事者双方の認識の相違などから思わぬトラブルに発展する恐れがあります。
契約書を作成することで、当事者双方が確かに合意したという証拠物とすることができ、トラブル防止の効果が期待できますので、贈与を行う際は契約書を作成することをおすすめします。
2.預貯金を移動
親名義の口座から子供名義の口座へ送金、もしくは親名義の口座から出金した現金を直接子へ手渡しするという方法が考えられます。
3.贈与税の申告(必要な場合のみ)
贈与税とは、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、一定の要件を満たす場合は「相続時精算課税」を選択することができます。
贈与税は、贈与を受けた方(財産を受け取った方)が贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの期間に税務署に対して申告と納税をする必要があります。
「暦年課税」
「暦年課税」の場合は、1月1日から12月31日までの1年間で贈与により取得した財産の金額のうち、暦年課税の基礎控除額である110万円を超過した金額に対して贈与税が課税されます。
よって、1年間で贈与により取得した財産の金額が110万円以下の場合は、贈与税は課税されないため、贈与税の申告は不要となります。
「相続時精算課税」
「相続時精算課税」とは、原則として、60歳以上の父母または祖父母(贈与者)から18歳以上の子または孫(受贈者)が贈与により財産を取得した場合に選択することができる贈与税の制度です。
相続時精算課税を選択する場合は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの期間に税務署に対して、相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
なお、一度、相続時精算課税を選択するとそれ以降は暦年課税を適用することができなくなりますのでご注意ください。
相続時精算課税を選択した場合、1月1日から12月31日までの1年間で贈与により取得した金額から相続時精算課税の基礎控除額である110万円を控除し、さらに特別控除額である2500万円(前年以前にこの控除額を適用していた場合はその控除額を除いた額)を控除した残額に対して贈与税が一律20%課税されます。
相続時精算課税は、110万円の基礎控除額に加えて2500万円の特別控除額があるため、まとまった金額を一括で贈与する際に、贈与税の課税を避けるという点で一定の効果が期待できます。
前述の通り、贈与時に有利な制度である一方で、贈与者がお亡くなりになったとき、相続税の計算上、相続財産(故人の財産)の金額に、相続時精算課税を適用して贈与した財産の金額を加算して相続税の計算をする必要がある点には注意が必要です。
相続税については本記事の「預貯金の相続」にてご説明させて頂きます。
預貯金の相続
「相続」とは、故人の財産や権利義務を相続人が承継することをいいます。
相続人の範囲と順位は民法で定められています。故人の配偶者は常に相続人となり、配偶者に加えて相続人となるのは、以下の範囲です。
① 故人の子(子が故人より先にお亡くなりの場合は孫)
② ①がいない場合、故人の直系尊属(父母や祖父母)
③ ①②がいない場合あ故人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人より先にお亡くなりの場合は甥姪)
死後に親の預貯金を子(相続人)が承継する行為は「相続」となります。
預貯金を相続する手順
- 戸籍の収集(相続人調査)
- 遺産分割協議
- 預貯金の解約申し出
- 相続税申告(必要な場合のみ)
1.戸籍の収集(相続人調査)
役所で相続人全員の戸籍と故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集し、相続人を確定させます。既にお亡くなりの相続人がいらっしゃる場合などは、さらに戸籍を収集する必要があります。
収集した戸籍を確認し、誰が相続人であるかを確定させます。
2.遺産分割協議(遺言書がない場合)
預貯金の相続に限らず、故人の不動産の名義変更など相続の手続きにおいては、原則、相続人全員の合意が前提となります。相続人全員で故人の財産の分割方法について協議する必要があります。この協議のことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご覧頂ければと思います。
【争続を防ぐ】遺産分割協議書とは?協議の流れや書き方・注意点を解説
故人が遺言書を残していた場合は、原則、遺言書の内容に沿って故人の財産を分割することとなり、遺産分割協議は不要です。しかし、相続人全員が合意しているのであれば、遺言書の内容に沿わない遺産分割協議をすることも可能です。
3.預貯金の解約申し出
金融機関に必要書類を提出し、故人名義の口座の解約申し出を行います。金融機関によっては、解約ではなく名義変更での取り扱いも可能な場合があります。
解約申し出に必要な一般的な書類は次の通りですが、金融機関により異なる場合がありますので、お手続きされる際は各金融機関にお問い合わせ頂ければと存じます。
- 戸籍謄本(「1.戸籍の収集」にて取得したものすべて)
- 相続人全員の印鑑証明書(金融機関ごとに3か月または6か月の発行期限あり)
- 故人名義のお通帳
- 代表相続人名義のお通帳
- 金融機関所定の解約申し出の用紙
解約申し出が受理されると、故人名義の口座が解約となり、故人名義の口座の残高が代表相続人の口座へ払戻しされます。金融機関によっては、遺産分割協議の分割方法に則り、各相続人の口座へ払戻しをしていただけます。
4.相続税申告(必要な場合のみ)
相続税とは、相続に係る税金です。故人の財産総額から基礎控除額(3000万円+相続人の人数×600万円)を控除した残額が相続税の課税対象となり、故人がお亡くなりになった日から10か月以内に相続税の申告と納付を行う必要があります。
故人の財産総額とは、原則として故人名義の預貯金や不動産、有価証券、自動車などの価格の合計です。これら以外にも、相続税の計算上、みなし相続財産として生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金、相続時精算課税を利用した贈与財産なども故人の財産総額として相続税の対象となります。
したがって、相続手続きを進める際は、預貯金含め、故人の財産総額が相続税の基礎控除額を上回るかどうか確認していただくのがよろしいかと存じます。
故人の財産総額が基礎控除額以下の場合、相続税はかからず、相続税の申告も不要となります。
急ぎの場合は専門家へ相談する
札幌大通遺言相続センターでは、無料相談を実施しています。ご依頼いただく際のお見積だけでなく、あなたの状況に合わせて必要な書類や、多くの方が躓くポイントなどを解説させていただきます。
ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回は親から子への預貯金の「贈与」と「相続」について解説させていただきました。最後にポイントを振り返りましょう。
・生前に親から子へ預貯金を無償で渡す行為は「贈与」となる。
預貯金を贈与する手順
- 贈与契約書を作成
- 預貯金を移動
- 贈与税の申告(必要な場合のみ)
・死後に親の預貯金を子が承継する行為は「相続」となる。
預貯金を相続する手順
- 戸籍の収集(相続人調査)
- 遺産分割協議(遺言書がない場合)
- 預貯金の解約申し出
- 相続税申告(必要な場合のみ)
「必要な書類がわからない」「書類の書き方が正しいのかわからない」「手続きをお任せしたい」などのお悩みがありましたら、札幌大通遺言相続センターの無料相談をご利用ください。
ラインでの受付も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。